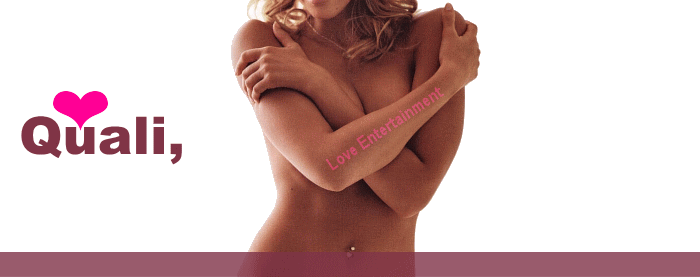4.gif)
16.「ATフィールド」の陳腐性
エヴァンゲリオンの最終話が2021年に上映されて、ファンたちにとっては「ようやく」という心地があったそうだ。
その「ようやく」というのも、半ば「もう正直どういう形でもいいから」という思いがあったと仄聞している。
旧劇から新劇まで十年が空いていて、新劇から最終話まで九年も空いているのだから、もう心待ちにするのも「待ちくたびれる」ということが起こるだろう。
若い誰かがエヴァにハマったとしても、九年もたてばもう別の人だ。特にこのごろは数か月で趣味も考え方も入れ替わっていく人が多い。
東日本大震災があったあと、新劇Qがあって、そのQも内容としては、「破」の前フリからなぜか逸脱した行方不明のもので、観た感想としては「何か赤色と黒色がンゴゴゴゴしていた」という漠然とした記憶しか残らない。これを三部作のクライマックスにあてがわれて失望した人はきっと多かっただろうと想像する。そこから九年も経って最終話となれば、ファンとしても「もういいよ」という気持ちがあって当然だろう。
最終話として示された「シン・エヴァンゲリオン」だが、わたしの言うところもともと「話」は存在していないので、そこに「最終話」など当てはまりようもない。強引に農村の暮らしを見せられた後に、北斗の拳のように人がパンッと爆ぜるのを見せられて、シンジ君がいつもどおりぐずり続けるモードに入るというようなことだった。
そして最終的に、「駄々っ子シンジ君」の問題は、唐突に「駄々っ子父さん」に転移されてエヴァンゲリオンは終わる。たぶんこの展開を、エヴァの長年のファンたちはいろいろと無感情で見遣ったのではないだろうか。
ここに示されたのは、一昔前の「機能不全家族」のようなもので、けっきょくすべてのテーマは「家庭内の痴話」というような、最も小さなものに押しやられた。人類補完計画やら◯thインパクトやらいうウソ話はもちろんまともになかったことにされ、駄々っ子父さんと駄々っ子シンジ君のお仕着せの問答が一種お約束の空気の中で進行していく。
そして最後は、もはやエヴァでもなければ碇シンジでもない、粗雑に作られた「リア充」みたいなものを見せてサッと逃げ去る。それはもはやしょうがないことだ。初めから話などないものを、最終話で締めくくることなどできようがない。そしてそのことをファンたちは、一種のファンマインドのようなもので見送ったに違いないだろう。「ある意味、最後まで、らしいといえばらしい」みたいな心地はあったかもしれない。
この機能不全家族の痴話の発端は何か。発端はいわずもがな、「ゲンドウ君のATフィールドだ」ということになる。
ATフィールドとは何のことかというと、言うのも気が引けるが「こころの壁」だ。そんなものがあるのかどうかも不明だが、誰でも思春期に一度は感じるであろうそれのことだ。
そして実はこのことは、すでにサルトルが1940年代に発表している。もちろんATフィールドという名前で発表したわけではないが、
「地獄とは他人のことだ」
という決めゼリフに向かって、「出口なし」といういかにもそれっぽい戯曲がサルトルによって書かれ、上演されている。
「他人」の存在を地獄そのものと感じ、その壁に向き合っては、アンガージュマン等々と、正直無理のある屈曲をした人としてサルトルはよく知られている。一般的には哲学者とされているが、どちらかというと小説家で、サルトルは哲学者ではなかったからこそ、その言い分は一般によく共感された。同時期の哲学者というとたぶんフッサールなどだが、そういう本腰の入った哲学というのはほとんど一般の人びとには理解しえないものだ。哲学のほとんどは一般には「これが何に使えるの?」と疑問に思われて棄却される。哲学は共感するものではないから……その点サルトルの言い分はよく共感に響いたので一般にも知られている。
サルトルのテーマは「他人という地獄にどう向き合えばいいのか」「世界は何もかも無意味で、よくよく見たら無意味すぎてグロテスクでゲロ吐きそうだ」というようなことだ。誇張ではなくこのとおりなのでこれはわたしの言い方が悪いのではない。
話・ロゴスに視力のない人が「神」うんぬんを視認しようとすると、「グロテスクな何か」を見てしまうということは、サルトルおよびクトゥルフ神話などで知られている。クトゥルフ神話は神話ではなく、そういうゲーム小説のようなものであり、そういう企画で作られたイメージ群のことを指す。ラブクラフトという作家が発起人だ。
サルトルの言い分は、1960年代の実存主義から1980年代のポストモダン後ぐらいまでいじられたから、当時を生きたクリエイター系がサルトルのパターンを知らないはずがない。知らないはずがないどころか、これは当の世代においては「ド定番」のひとつでさえあるはず。
碇ゲンドウにせよ碇シンジにせよ、「他人」に対する恐怖とその壁を感じ、その壁の向こうに踏み出そうとすると、「対話不能の、巨大かつグロテスクなものを視る」「そして正気度(SAN値)を脅かされる」というのは、そうしたサルトルやクトゥルフ神話で過去に説明済みのものだ。
そして、果てなき射精主義や、母親を女性とする恋慕等、性的欲求不満から生じる心象も、深層心理学がすでに解明済みの範疇を出ない。
だからこれらはすでに過去に使用済みの何かを力一杯に寄せ集めただけであって、そこに描かれているものに斬新さはない。ただ、1980年以降に生まれた人はサルトルのことなんか知らないので、思春期に覚える「他人」への恐怖と壁を劇的に表示することは斬新に見えたかもしれない。たとえば洋楽に疎かった日本人のところに、洋楽のサウンドを持ってきてさも斬新なふうに流行をさらっていった音楽プロデューサーがいたように、原本がすでにあることを隠匿されると視聴者はそれを新しく彼に生じた独自のものと思ってしまう。
何が斬新かといえば、これをアニメーションというメディアに徹底的に詰め込んで、「話」ではない「パトス亢進ビデオ」として成り立たせてしまったところだ。まるで新世紀エヴァンゲリオンという「映画」ではなく「製品」があるようなものだ。モンスターエナジーというようなノンフィクションの「製品」があるように、新世紀エヴァンゲリオンというノンフィクションの「製品」がある。
エヴァというビデオの発端であり始末でさえある、その象徴たる「ATフィールド」を説明しきると、すべてのことに冷静な決着がついてくる。
ファンの人たちは重々知っていることだろうが、ATフィールドは absolute terror field だ。直訳すると「絶対恐怖領域」となる。
つまりシンジ君がいつでも言いそうな、
「イヤだよ、怖いよ、ぜったいイヤだよ、こんなのまるで地獄だよ」
のことだ。
そしてシンジ君だけでなくゲンドウ君も同じそれのユーザーだ。
サルトルも同じ、「他人」というと、それこそが地獄だという。
なぜそれが地獄なのかについて、つまりATフィールドについて、エヴァ作中にではなく、サルトルの作中に訊けばよい。「他人」はなぜ怖いのか。なぜ絶対恐怖領域なのか。
戯曲「出口なし」の中でその理由は表示されるのだが、ここではわたしが単純に説明しよう。
<<自分で自分に「自信」を認められない場合、自分に他人が入り込み、その入り込んだ他人が自分を認めてくれるかどうかが「自信」を決定することになる。ここにおいて、入り込んだ「他人」はわたしの支配者だ。けれども他人はけっきょく、自分のことを認めてはくれない。それで自分は永遠に自分を肯定できないことになるのだ。他人はそれほど恐ろしくて、それじたいが地獄の存在だ>>。
この恐怖と地獄があって、「他人に絶対に入り込まれたくないよ!」という拒絶の叫びが起こる。「僕の中で出口のない地獄が始まるんだ!」「もう絶対に逃げられなくなるんだよ!」。それがエヴァ作中で大げさに「ATフィールド」と呼ばれているだけだ。
主体性のないところに、「他人」に入り込まれたらオワリ、永遠に逃げられない地獄の始まり、だから絶対に入り込ませないということ。
いま、
「主体性が無いんだ?」
と言えばそれだけで用は済む。
シンジ君にではなくゲンドウ君に言え。
主体性がないから、自分を肯定してくれる他人を必要とする。
あくまで自分のために必要とする。
それが綾波ユイだったから、それに生き返ってもらおうと必死だ。
と、いちおう形式的には言いうる。
だがそれは、最大限「作品」として観ようとしても、碇ゲンドウというおじさん一人に関わることであって、エヴァやら使徒やらには何の関係もない。ゼーレにも補完計画にも何の関係もない。
主体性がないおじさんが自分を肯定してくれる人を必死に募集中というだけだ。
そういうおじさんが、いるにはいるだろうねというだけであって、何の「話」もない。
正直なところ、「ATフィールド」の演出にわらわら視聴者が集まってきたことについては、それより三十年前、サルトルの実存主義にわらわら大学生が集まってきたことと差分がない。
冷静に考えればわかることだが、
「ATフィールドが "ある" 」
のではなく、
「主体性が "無い" 」
のだ。
とんだ取り違えだが、実存主義の時代にも同じ取り違えをしていたのだから、当事者としては陥ってしかるべき取り違えなのかもしれない。
「ATフィールドを展開!」というと、フレーバー的にかっこいいと誤解するかもしれないが、「主体性が無いを展開!」というと、絶望的にカッコ悪いし、リアルに考えて「気持ち悪い」だろう。
ただ、「主体性が無いを展開」ということであれば、それはいちおう、「話」にはなっている。
シン・エヴァンゲリオンでは、ATフィールドで固めただけの液体人形が、エネルギーを使い果たすと「もう無理」となってパンッと弾けて死ぬという描写がされた。
ATフィールドがあるのではなく主体性が無いのだ、液体人形に主体性はない。
それを「かわいそう」として、感情、感受性、パトスを詰め込んで、射精しようということ。可能なかぎりのパトスをチンコに積んで大発射。その無上の射精にまで到達したら、その向こうから神話がやってくる……
いや、神話はやってこないだろう。
それでどうなるかというと、やはり先の例から逸脱はせず、その轍を踏んでいくことになる。
いかにも無理のあるリア充っぽい何かになるしかないのだ。
冗談ではなく、サルトルの実存主義はそういう結論に至っていて、シン・エヴァのラストシーンは、そのサルトルのアンガージュマン結論そのままだ。
「社会的に自分に要請されるものを取り込んで、それをエセ主体性にし、社会と友好関係にあるリア充のふりをし続けましょう」というのがサルトルの結論だった。
(実存主義時代はそれで魂が解決すると信じた人がたくさんいた)
けっきょくエヴァンゲリオンという試みにおいて、パトスを神とし、無上の射精が天国のはずとする追求は、あっさり失敗に終わった。
それでラストシーンは、似非リア充として "妥当な射精" を存分にしつつ、「やっぱりサルトルなんすかね〜」だ。
サルトル以前だったらこのラストにはまだ希望が見出し得たかもしれない。
だが誰だって、サルトルの実存主義は成功しなかったことを知っている。
何しろ当のサルトル自身が、その実存主義について後には「知らんぷり」を決め込んだのだ。
そのことに当てはめれば、このエヴァだって、作り手が最後に「知らんぷり」を決め込んだと言えるだろう。
というわけで、徹頭徹尾、新世紀エヴァンゲリオンなんて「話」はなく、主体性のないゲンドウおじさん、その子供時代の、主体性のないシンジ君、せいぜいそういう「モデル」があるだけだった。
その他のすべては、何度も言うようにパトス実験に供されたパトスのオカズにすぎない。
わたしはこのエヴァのファンではないので、顛末について感慨も持たなければ是非の思念も持たない。
わたしが主題としているのは、二十五年前、このエヴァが代表的なひとつのトリガーとなって、人びとに「ロゴスとパトスの錯誤」をもたらしていったことだ。
二十五年前に点火したものが現在どのように燃え広がっているかということにわたしとしての焦点がある。
そのことは後半に述べられてゆくだろう。とりあえず、一連の劇場版エヴァを題材とした考察ならざる解説は以上となる。
←前へ 次へ→