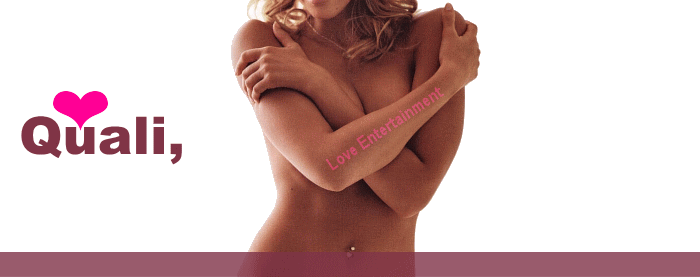4.gif)
23.旧来のパトスには揶揄があった
人の魂にパトスがあってはいけないということではない。
パトスとロゴスがあったとして、仮にもともとの福音書をあてにするなら、「ロゴスが神であった」ということだ。
パトスが存在してはいけないとは言われていない。
たとえば四コマ漫画「コボちゃん」や「かりあげ君」があったとする。
「かりあげ君」の中に、競馬に入れあげてスッテンテンになる者、女の色香に吸い込まれてヨダレを垂らす者、誰かと言い争いになって「この野郎」と殴り合いに及ぶ者、などが描かれたとしよう。あるいは恋人にフラれて落ち込む者、事業に失敗して「もう首をくくるしか」と思い詰める者なども描かれてよい。
そのことがわれわれに、福音書の書き換えを迫ってくるとはまるで思えない。何しろ「かりあげ君」の作中のことだ。
旧来のマンガ等でパトスが描かれるときは、パトスは十分な「揶揄」のもとでそれが描かれていた、ということがわかる。
パトスが描かれているには違いないが、それ以上に主題たる「話」があって、パトスが専横を振るってはおらず、パトスの描かれ方は「シリアスでない」ものだった。
ロゴスたる「話」の直下にて、パトスはその権威の範囲を制されており、しょせん「やれやれ」と揶揄されるものでしかなかった。
「きれいな女に勧誘されて、ついていったらサギで……」
「ばかだなー」
そういうやりとりが「かりあげ君」や「おとぼけ課長」に描かれているとき、そこにあるものは何らシリアスではなく、それでも憐れみや痛みを伴って「やれやれ」と感じられる。
のび太がジャイアンにいじめられて、
「ドラえも〜ん!」
と泣きつくとき、ドラえもんも視聴者も、
「やれやれ」
とのび太に同情するまでであって、のび太を「被害者」としてその哀号を主題にするわけではなかった。
あるいは古い時代、若い男が色っぽい女に「おっ」と反応すること、あるいは若い女性が高価すぎるイヤリングに「まあ!」と反応することなどは、すべてその「やれやれ」の範疇だった。
けれども現代において、ロゴスは立ち去りすでにその権威の庇護はなく、パトスが第一の神となって、
「あーマジ、あのエロ女とやりてー。何なんあのカラダ、えっちすぎるだろ。誘っているというか、マジでああいうのって歩くセックスというか、セックス専用女だよな。あんな女ぜったい人生イージーモードだし、マジぶちまわしてえ。絶対すごい精子出るわ。この話わかるでしょ」
「仕事を見て盗めとかマジで意味不明。それで、あれこれ聞いたら怒るくせに、トラブったら『なぜ聞かなかったの』とか、ダブスタにもほどがある。労基はこういうことまでケアして、違反したら罰則をもうけるべき」
「これさあ、元カレっていうか、向こうは彼氏のつもりのお客さんからもらったイヤリングなんだけど。調べてみたらもともと十二万もするらしいね。なんかね、それを知ったとき、ああもうすべてを許そうと思った笑。けっきょくさあ、そいつがこっちに使ったトータルの金額で、許せる・許せないかって決定するよね。この話わかるでしょ」
これは「やれやれ」の範疇を逸脱している。彼らの神たるパトスは、是非の以前に酸鼻であり、いかなる揶揄もその瘴気を打ち払いはしないだろう。
パトスがあってはならないということでなく、それが第一の権威・第一の神となると、われわれの現代のような状況になるということだ。かつてはロゴスがパトスを見下ろしており、パトスは「やれやれ」という揶揄の範囲で済んだが、そこに全体として帰ることはもう出来ない。
←前へ 次へ→