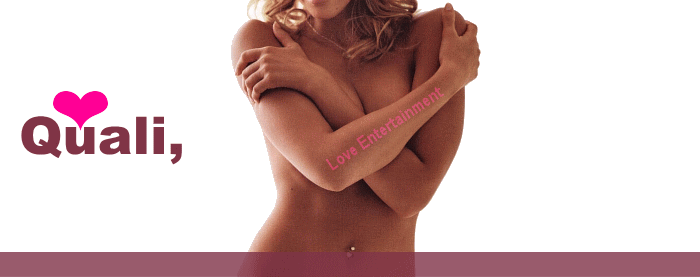4.gif)
7.碇シンジは何をやっているか2:フラストレーション
碇シンジは感情・パトスの無限大化に向かっている。
その無限大化の行程に、パトスの解消があってはならない、感情を目減りさせている場合ではないのだ。
よって碇シンジは、パトスが解消せず鬱屈・蓄積していくようにデザインされる。
あくまで、そういう「話」になるということではなく、ただ鬱屈・蓄積していく「だけ」だ。
どのようにその鬱屈・蓄積を為させるかというと、「フラストレーションによって」ということになる。
フラストレーションは「挫折」という意味だ。
通例に「フラストレーションが溜まる」という言い方があるが、これは「挫折によって感情の鬱屈が蓄積する」という意味だ。「やり場のない感情」と言うとわかりやすいか。
とはいえ「話」があるわけではないので、碇シンジは漠然とその「挫折」と鬱屈の蓄積によってフラストレーションを溜めていく、そういう映像がだらだらと繰り返される。
事実の照覧は何ら必要ではなく、ただ、
「僕は何をしてもダメなんだ」
「ぜんぶ僕のせいなんだ」
「何もかもがどうせ裏目に出る」
「誰も僕のことを必要としていない」
等、事実であろうがなかろうが、自分でそう思い込んで反芻していけば――そういうことにしておけば――そのぶんフラストレーションは溜まる。
ここでまた、「視聴者」の存在を仮定すれば、視聴者はある種の性質において碇シンジのパトスに共感して引き込まれていく。
言うにもいささか憚られるが、つまりは "根本的に挫折して生きている人" に共感を呼ぶのは構造としていかにも当然だ。
碇シンジは「話を聞かず、挫折を繰り返す」という自動的な装置であって、解消されることのないパトスを蓄積していく。
一時的にその解消をギミックとして与えられることはあるが、その後は必ず倍にして回収されるようになっている。
あくまで、そんな「話」があるわけではなくて、ただそういうふうに絵を動かし、そういうフレーバーだけ漂わせている、ということが示されるだけではあるけれども。
こうして碇シンジは、根本的に挫折して生きている人たちに「神話がある」と触れ込んで、呼び込むイコンと化す。ただしけっきょく神話はない。「話」がないのだから神話があるわけがない。あるのはあくまで感情の無限大化だけだ。「それじたいが神かもしれないじゃない」という、投げやりな思いつきが執拗に実行されたと見ていい。
その感情の無限大化がどうなるのかについては、たぶん作り手側も「さあ」と知らない。このことに作り手の執念はあっても意欲はない。作り手側も「やってみたかった」という感情だけがあるのであって、何をやったかという話があるわけではない。これを作ることじたいに話がないという点で、取り組みは徹底していると言える。
←前へ 次へ→