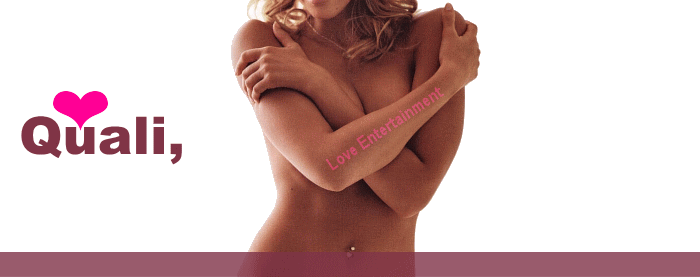4.gif)
22.パトスを「話」だと思うようになる
麻薬中毒者は、麻薬によって得られる興奮・快感・安らぎを、「真実」だと確信してそれを内心で標榜する。
それは当然、麻薬による体験が「真実でない」と感じられるなら、そのことに嵌りこみようがない。
麻薬を売る業者の側は、麻薬による体験はすべてウソだと確信しているが、麻薬を買うユーザーの側は、麻薬による体験をけっきょく真実だと感じている。
だからよく知られているように、麻薬を嗜好するグループは、確信において他人を「勧誘したい」と常に思っている。
マジ最高だから、と思っているのだ。一方、その麻薬を売りつけている側は、その光景を「マジ最悪の、地獄だな」と眺めている。
パトス洗礼によって「話」が視えなくなったとして、何もかもが視えなくなるわけではない。
逆側、パトスの側に決定的な「何か」が視えはじめる。
それは神話ではないか、というのがエヴァの立脚点だった。
パトスの向こう側に神話が現れてくるのならば、旧来の福音書は書き換えられなくてはならないだろう。
パトスの徒は、ロゴスたる話を失認するのみならず、話ならざるパトスの色を、「話」だと誤って視認するようになるのだ。
パトスの徒は、けっきょくパトスが「話」だと思うようになる。
さきほど「サマーウォーズ」の例を出したが、長野県の山中の長屋というフレーバーにおいて、あこがれの先輩にやさしく微笑みかけられるということが、
「それが、僕の夏だった」
というふうに視えはじめるということ。
「それが僕の、青春の話」
というふうに視えはじめる。
ただしこのことは、もともとから破綻している。破綻しているからといって、その当人において「瓦解」するわけではないが……
美貌を誇り、闊達で人気者のあこがれの先輩が、地味で目立たない後輩に突如、わたしの疑似婚約者たれとの白羽の矢を立てはしない。
もしそんなことがあったとしたら、それは悪徳商法のセールスだ。
そのあこがれの先輩の挙動が「設定」で無理やり固定されているから、そのような展開が捏造されるのであって、そのような女性の「話」はないし、そのような展開の「話」もない。
ただ、だからといって、
「それが、僕の夏だった」
というパトスが止まるわけではない。
止まることのないパトスは、いかなるロゴスの破綻を踏み越えてでも、それはそういう「話」だったと信じることを選ぶだろう。
「話」ということの定義じたいを書き換えることになる。
このことが進行すると、たちまち奇妙なことが起こってくる。
それは、ロゴスが破綻していればしているほど、それが「話」として "馴染みやすく" なってくるということだ。
「ギルバート財団の御曹司でありながら、世界屈指の頭脳を持つミナトにとつぜん求婚されるヒロイン。一方、聞かん坊の幼馴染ミツルは、『三歳のときに結婚を約束した、彼女はそのときからおれのものだ』と言ってきかずに大暴れ。二人の男の引っ張り合いに、思わず悲鳴をあげるヒロイン。『やめてよ、わたしはお裁縫のコンクールに出たいだけなんだってば!』。圧倒的な財力・知力を持つミナトに対し、ミツルが突如明らかにした彼の秘密の能力とは? それぞれ一歩も引かない三者はどのようなゴールに行き着くのか、留まるところを知らないドタバタ青春コメディ!」
このような「設定」が、女性のいかにも偏った願望・パトスから――あるいはそれに向けて――生じているのは明らかだ。「そんな話があってたまるか」と理性的には苦笑している。
けれども実際には、このようなマンガなり読み物なりが自分に「馴染む」ということが起こる。
「読んでてラクというか」
「割とフツーに面白い。で、あーそういうのわかるとか、けっこう泣かせにくるところもある」
「雨ん中でミナトが立って待っているシーンまでは絶対読んだほうがいい。あそこまではマジ神展開だから」
「こういうフツーの面白い話を求めていたんだなあって我ながら思うよ、アニメ化とか正直すごい楽しみだもん」
この彼女に、たとえばこのような話を向けてみる。
「応仁の乱以来、足利幕府は自壊を起こしてその力を弱めていった。幕府恐れるにあたわずとなると、各地の大名が勢力を伸ばしてくる。戦国時代の始まり。そしてついに最大勢力のひとつとなった今川家が京都に上洛しようとしたとき、その道中でまさか弱小勢力の織田家に討たれた。こうなると、もうどの勢力が覇権を為してもおかしくない。織田家が京都(室町)まで支配するようになるともう足利幕府は無いに等しいから、室町時代ではなく安土桃山時代となる。この安土桃山時代は、関ヶ原以降、徳川幕府が成立して終わる。以降が徳川幕府・江戸時代だ」
彼女はどう応えるかというと、
「ふーんそうなんだ。なんか、ぜんぜんピンとこないけど笑。歴史笑」
そして必ず、
「あー、思い切って化粧水、ぜんぶ高いのに変えちゃおうかなー」
というようなことを唐突に言う。
パトスの聖水だ。
パトスの水をかけてロゴスを解体しようとする。
(このことは必ず・不可避に起こるので、無理に押しとどめようとしなくてかまいません。無理に押しとどめるのはけっきょく精神に過大な負担をかけます)
表面上、いろんな反応があるが、どれもパトスの水でロゴスを解体するということ、および「パトスを話と思う」ということに変わりはない。
化粧水の話をブッ込むということはしなくても、代わりに、
「そうなんですね! それが戦国時代なんですね!」
というパトス挙動でその解体をする。
あるいは、「話」は視えないけれども、言われた文言を丸暗記し、そのままなぞる、ということもする。
「合ってますよね」
学校のテストなら高得点を与えられるので、正解・成績優秀というパトスが補充されるかもしれないが、歴史の話というのは学校の課題ではなく単に「過去の人びとがやったことの話」だ。合っているからといって点数になるという現象はそもそも存在していない。
ここでは「エヴァ」を皮切りに話したものだから、話の対象はあるていどその世代に寄せている。けれども高齢者層でも現代における様相は同じだ。
パトスを「話」と思っている。
「この齢になってね、もう自分のことはいいんよ。ただ、娘のことが、いつまでもどうしても気がかりでねえ。どこまでいっても、それは親と娘やろ? どうかあの娘が幸せになるところだけは見たいと思って、そのことだけが胸を苦しゅうしてしょうがないんよ」
というのが自分の「話」だと思っている。
街中で激昂している、ないしはその顔つきに激昂を溜め込んでいる老人を見つけることはそんなにむつかしくないが、彼は何に激昂しているかというと、何にということは主題ではなく、
<<自分が激昂しているということが「話」だと思っている>>のだ。
老人でなくても常に激昂している人たちは現代に数多くいる。
何に怒っているというようなことではない。
すべて、ロゴスたる「話」のすべてが失われ、パトスを「話」だと思うようになったことで生じている。
「この感情こそ本当の自分」
その感情は強く・深くなくてはならず、日々の練り上げが求められる。
つまり、わたしがこうして果てしなく「話」をすることの裏側で、果てしなく「感情」をする、ということが人びとに行われ続けてきたということになる。おれが話をしているあいだ人びとは感情をしてきた。それはわたしの知らない、わたしから見て裏側の二十五年間だった。
←前へ 次へ→